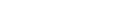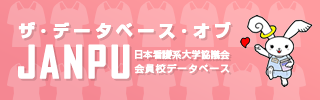今は子どもファーストで生活していますが、家族は私の専門を理解して、災害現場に行くときは最大限サポートしてくれます。
今は子どもファーストで生活していますが、家族は私の専門を理解して、災害現場に行くときは最大限サポートしてくれます。
- 兵庫県立大学・地域ケア開発研究所(客員研究員)
- 藤田 さやか
広島県立保健福祉大学(現県立広島大学)卒業後、大阪府立中河内救命救急センターで臨床経験を積み、2010年から2012年、JICA海外協力隊としてウズベキスタン共和国で活動。2014年から兵庫県立大学大学院看護学研究科共同災害看護学専攻5年一貫制博士課程(文科省博士課程教育リーディングプログラム:災害看護グローバルリーダー養成プログラム)に在籍し、国内外の災害支援の活動に携わるようになる。2019年に学位(看護学博士)を取得。姫路大学看護学部グローバルヘルス領域の教員を経て、ワーク・ライフ・バランスを追求した結果、2023年より現職。
適度な共感力と想像力を養うため、リアルな現場の事例を伝えていくこと
私の母は若年性乳癌で10年の闘病の末、40歳で死去しています。立て続けに同居していた祖母も癌で亡くしました。2人とも長期に自宅療養をしており、自分に知識があればもっと支えることができたという悔いを糧に看護の勉強を始めました。面接で、看護師を目指した理由を聞かれると、それが自分の運命だと思っていると答えた記憶もあります。こと患者家族への共感力が高すぎて、実習では感情移入をしてしまい、精神的に辛くなったり、そんな自分を責めてしまったり、悩ましい学生時代を送りました。本能的に、終末期ケアと距離を置きながらも、最大限資格を活かして活躍したい思いを馳せて、卒後は救命救急センターに就職しました。そこで型にはめられない症例にたくさん出会い、知識や技術というものではなく、もっと感覚的な何かが足りないことを不安に感じ、思い切って自分探しの旅に出ることにしたのです。「思い立ったらすぐ行動」で、2週間で書類を揃えて申請したJICA海外協力隊の試験に合格し、ウズベキスタンに派遣されました。
生真面目な性格に加え、救命救急センターでたたき上げられた私には、赴任国の「運命は神様が決めているから」や「あとで、っていったら明日かもしれないし1週間後かもしれない」というような、曖昧にするような文化が性に合わず、最初は思い通りにいかない苛立ちや虚無感でいっぱいでした。しかし、「予防の概念やエビデンスの重要性が通用しない」のはなぜだろうというところに関心を持ち、のちに出会うレイニンガーの異文化ケア理論を、知らずに実践してみたことにより、自分の価値観を押し付けていたことに気づきました。相手の文化・価値観を理解しようと思うようになってからは、自然と気持ちが通じ合うようになり、看護も日常生活もとても楽になる経験ができました。一方、日本の看護や看護教育の質の高さを改めて実感するとともに、自分の経験を日本で還元したいという思いを抱きました。中でも、年間360日は晴れるという地域で「60年ぶりの豪雨から2時間後に豪雪」という稀有な災害に遭い、1週間の停電・断水の中で生活した経験が、災害看護の道に進んだ理由でもあります。また、途上国支援をしに来たのに情報弱者となり心細い思いをした経験が、私の研究テーマでもある、「異文化下で生活をする人(訪日・在日外国人)への災害支援」への関心につながりました。
災害看護を専門としてからは、医療チームや学会の先遣隊に登録して、国内外への災害現場には積極的に赴くようにしています。災害看護活動をかっこいいと思う学生さんもいれば、自分にはできないという学生さんもいます。でも、いつどこで起こるかわからない災害に備えなく遭遇することのないように、被災者の思いに触れ、生活の現状を見て聞いて感じたことを、教育現場に還元することを続けています。災害看護はまだまだ発展途上の分野ですが、妊娠中から災害現場に連れて行っていた長男、コロナ禍で産まれた次男も、今ではなんとなく私の仕事を理解して「お母さんのように困っている人を助ける仕事がしたい」と思ってくれているし、どこかで災害が起こると「またじしんのところに行くの?」と、自分の生活に惹きつけていることを感じます。災害現場に関わらず、看護が関わるどんな場面でも、感情移入しすぎず、かつ他人事にしないことで、寄り添いが実現すると考えているので、学生さんにも看護を専門とするためには適度な共感力が重要であることを伝えています。また、知らないことを知ることで不安はなくなり、似たような事例に経験が応用できるようになると、余裕が生まれます。不安でたまらなかった新人時代に必要だったのは、想像力だったのですよね。経験したこと、知っていること以上のことに対応できないのは当然ですが、未知の国や災害現場に飛び込んでみて、想像力が何事も切り抜けられる力になるものだと確信しました。私のアドバンテージである「知らないものに飛び込める勇気」を活かし、誰かの代わりに見て聞いて感じたことを、たくさんの事例として提供し、適度な共感力と想像力を養ってもらうこと、今はこれが使命であると感じています。